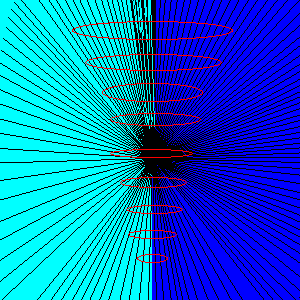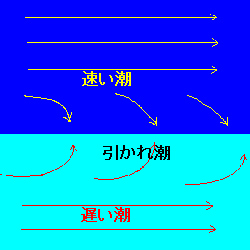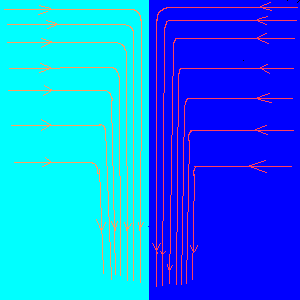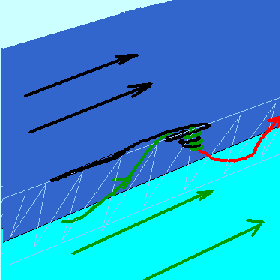2.潮流2 -潮目- もう一つ魚がよく釣れる場所
「潮目」について考えてみたい。
潮目は大きな物では黒潮と親潮の合流点に見られる物や、河川の流れ込みと海との合流点で生じる物など様々な物がある。
このページでは磯で見受けられる潮目についてコメントしたい。

またもや下手くそな絵をご覧に入れることになるが我慢していただきたい。
釣りをしていて海面をよく観察していると、周囲とは異なる表面をした帯を見つけることができる。
この帯が潮目と呼ばれる物である。
潮目とは2つの異なる流れの境目に生じる壁の事である。
この壁は絵をご覧のように、二つの流れの速度差から渦をともなっていると思われる。
では、同じ海でありながらなぜこのような速度差が生じるのだろうか。
それは海流が陸地に沿って流れるときに、陸地側にぶつかる抵抗があるからであろう。
地形・水深・水温の変化・障害物などにより幾つかに分かれた流れが再び合流する地点でこのような壁が生じていると思える。
また、水温が異なる海水同士がぶつかる地点でも潮目が発生する。
冷たい水は上から下へ、温かい水は下から上へと流れるのでこの2つの水域の接点は渦をともなっていることが多い。
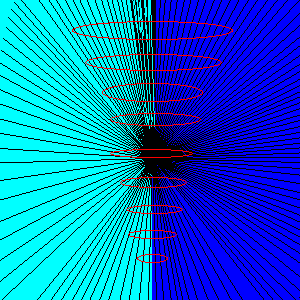
全くもってわかりにい絵で重ね重ね申し訳ない。
この絵はこの潮目の壁とそこに生じている渦を上からではなく、正面から見た感じを表してみたのだが、おわかりいただけるだろうか。
2つの流れの接点はこのように縦に長い渦を持っている。
つまり
この渦は上から下へと流れ込む渦、水中へ潜り込む流れではないだろうか。
但し、条件によっては湧き上がる渦、下から上へと流れ込む渦が生じる場合もあるだろう。
このページでは上から下へと流れ込む渦に注目してコメントしてみたい。 皆さんは鳴門海峡の渦潮のことはよくご存知だとだと思う。

潮の干満により海水が鳴門海峡を流れるときは海峡の幅が狭く、また急激に海底が浅くなっているため激しいスピードとなって通過する。
その際に周囲の流れとの差と海底の起伏によって大きな渦を発生させる。
通常我々が目にする潮目には鳴門海峡のような大きな渦ではなく、もっと小さな渦が幾つも発生していると考えている。
それでは次の絵を見ていただこう。
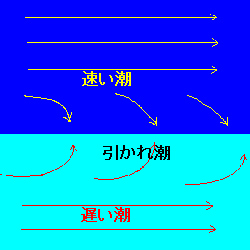
手前(下側)は陸地の抵抗で遅くなった潮、沖(上側)は早い潮。
2つの流れの速度差から陸側から沖側へと引っ張られていく引かれ潮となっている。
潮目は速度が異なる流れがお互い引き合いながら流れている。
海中に住むプランクトンは自力では泳ぐことが出来ない物が多いため、この引かれ潮に引かれて潮目へと集まることになる。
このプランクトン達を捕食するために多くの魚が集まる場所となっている。
また、陸地から撒いた撒き餌はこの引かれ潮によって潮の境目、つまり潮目へと誘導されることになる。
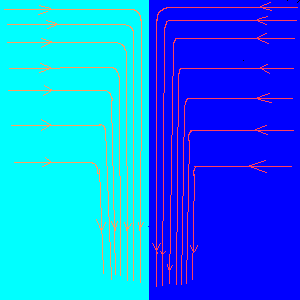
上の絵は引かれ合った潮がぶつかる地点を正面から見た場合の想像図である。
ぶつかった流れはお互いの力により下へと、海底へと流れ込んでいるはずである。
吸い込まれた流れはやがてその力を失いながら混ざり合っていくだろう。
この下へ吸い込まれていく流れも海中へと潜り込む流れだと思う。
再び変な絵をご覧にかけることをお詫びする。
まだまだ辛抱して欲しい。
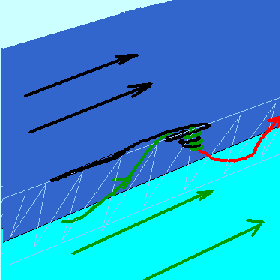
我々が放り込んだ撒き餌は、絵の緑色の引かれ潮によって潮目へと誘導される。
潮目では下に吸い込まれる流れや渦によって海中へと吸い込まれていく。
海中に吸い込まれた流れはやがてこの潮目の壁に沿って流れていく。
プランクトンや撒き餌はこの潜り込む流れや渦に集まってくるはずである。
魚たちがより捕食しやすい場所であろう。
特に最初に2つの流れが合流する地点は吸い込む力や渦は強い力を持っていると思える。
潮目の中でもこの下へ潜り込む流れと渦の中が魚を釣るのに最も好条件な場所といえるのではないだろうか。
さて潮目というのは沖に見えるはっきりとした物だけではなく、磯際や湾の出口、海底の障害物周辺など様々な流れの存在するところに小さな物が複数存在していると思う。
下の絵は磯の近辺の様子であるが、磯にぶつかったり陸地に沿って流れてきた潮流はぶつかり合ったり合流したりしているはずである。
この磯の周囲の潮流の合流点に小さな潮目が出来るはずである。

この小さな潮目は堤防や波止でもよく見かける。
上物と呼ばれるグレやチヌがなぜ潮裏でよく釣れるかは、磯際から離れた餌や人間が撒いた撒き餌がこの小さな潮目に集まっていて魚が補食しやすい場所だからだと思う。
そういった小さな潮目も重要なポイントと言えるのはご存じだと思う。
昔、お世話になった釣りの先輩にこういう話をしてくれた。
「本流で釣りをするときは、やみくもに流れの中に仕掛けを放っても無駄だ。」と。
先輩は潮目に沿って仕掛けを流すように教えてくれた。
本流釣りで流しても流しても自分には魚がヒットせず、隣で同じように流している人が多くの魚を釣り上げたなんていう過去をお持ちの方がいるのではないだろうか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・私だ(;^_^A
以上、潮流1・2の2項に渡って魚の釣れる場所を解説してみたがいかがだったろうか。
数が少なくなってしまった良型を釣るために、できるだけ高確率で効率が良いポイントを取り上げてみたのである。
釣りをするときは海の状況、陸地・海底の地形を読んで海中の流れと魚の位置を想像することは重要だと思う。
では、こういった海の中の変化のある場所ならば必ず良型がいるか・・・というと必ずしもそうではない。
ポイントにさえ仕掛けを放り込めば問題は無いか・・・アタリが確実に伝わるかというとそうとも言えない。
釣り人が魚を釣りやすいパターンというのがあって、そのときの海の状況、魚の活性、自然環境が一致しないとなかなか好釣果に恵まれないのが実際です。
理論は理論、実際の釣りに当てはまらないケースが多いことも事実で、未熟な私はまだまだ思案中です。