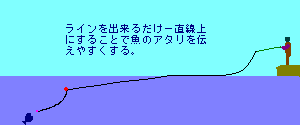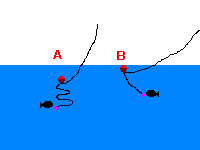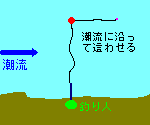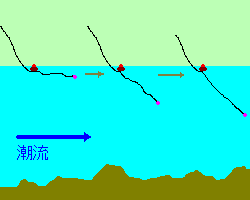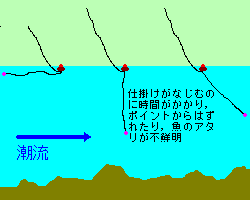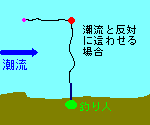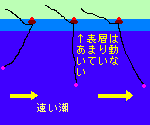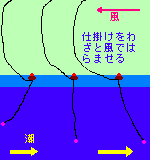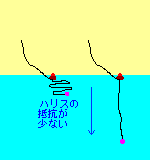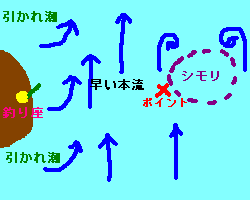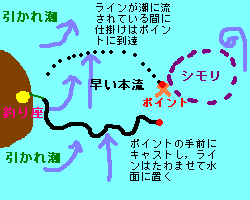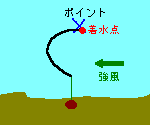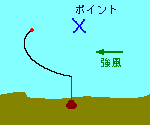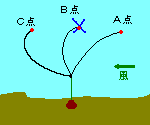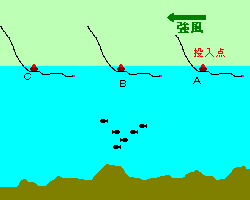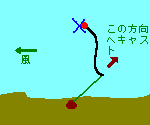キャスティング2
的確なキャスティングによってポイントに短時間で仕掛けを運ぶとともに、着水したあと道糸とハリスと刺し餌をどのように海面に置くかということもたいへん重要な事柄です。
置くという行動を間違えてしまうと、仕掛けが予想したものとは異なってあらぬ方向へ流されたり、餌をかすめ取られてばかりということにもなりかねません。
ただ単にポイントに仕掛けを放り込んで潮の流れに仕掛けを任せているだけでは,魚の口元に餌が届いてもアタリを感ずることが出来ない事が多々あります。
仕掛けを上げてみたら刺し餌が無くなっていて、本命?それとも餌取り?と考え込むこともあります。
着水時に仕掛けの置く方向,置き方を操作する事でより早く確実に餌を届け,アタリを明確に知るように操作しなければいけません。
どんな釣りでも同じことが言えるのですが、アタリを出来るだけ明確に素早くウキ(又は竿先)に伝えるためには,竿先から伸びるライン,ウキ,ハリス,針をできるだけ一直線上に置くことが近道です。
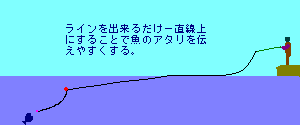
磯の周囲から流れる潮流にあわせて流していくだけならばたやすく一直線を形成することができますが、途中で餌取りに餌をかすめ取られたり、ポイントにたどり着くまでに長い時間がかかってしまいます。
また、サラシや払い出しの流れ・風の影響など様々な障害が仕掛けに影響してきます。
そこで、キャストとともにラインを海面に置く時に一工夫することが必要になります。
1、ハリスを置く
まず最初に仕掛けが着水するときに最初に海面に触れるハリス(針・餌を含む)の置き方を述べてみます。
下図は着水時のあまり良くない例です。
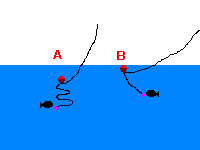
Aは仕掛けがたわんだ状態で着水しました。
しかもハリスが長いためたわんだままで魚が餌をついばんでいます。
Bは手前に伸びて着水しました。
逆の方向から魚が餌をついばんでいます。
いずれもこの状態ではウキ(又は竿先)にアタリを伝えることが出来ません。
何度も伸べるように自然や海の状況は一定ではありません。
海の状況に合わせた仕掛けの置き方を行うことで,いち早く仕掛けをなじませ,魚の口元に届けてやる方法を探り出さなければいけません。
次に幾つかのケースをあげて仕掛けの置き方の効用を解説します。
ケース1潮の流れる方向
通常魚達は潮の流れる方向に対して逆の向きに頭を向けて流れてくる餌を待ちかまえています。
早く仕掛けをなじませ,魚に餌を届けるために潮の流れと同じ方向に仕掛けを置いてやる事が重要です。
投げた方向に仕掛けを真っ直ぐに置くだけならば、ウキの着水時に道糸の出をちょっと指で止めてやるだけで振り子の原理でウキ→ハリス→餌の順で着水することは皆さんはもう実践されていると思います。
では、潮の流れが垂直ならばどうでしょうか。
キャストの時点で振り込む方向を変えてやるだけで上手にはわせてやることが可能となってきます。
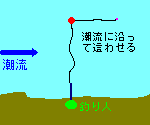
仕掛けをキャストするときに右側からサイドキャストで振り込み,潮流に乗るように這わせます。
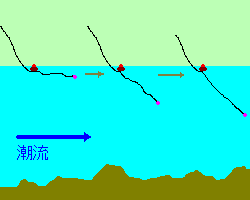
水面下では潮流に乗りながら仕掛けがなじみ,ラインが直線状になるのがわかります。
ここで逆に潮とは反対に這わせたらどうなるでしょうか。
海面下では下図の様になると想像できます。
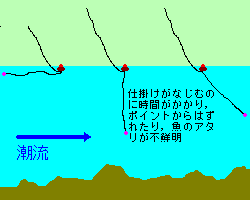
仕掛けがなじむまでに時間がかかってしまい,潮流に流されている間にポイントがはずれてしまったり,ウキに反応の現れないまま餌を取られたりする確率が大きくなります。
あまり無いケースなのですが、潮流が釣り人の方へと流れる場合はどうでしょうか。
そういうときはやはり手前にハリスが来るように置きます。
フリッピングというテクニックが役に立ってきます。
ケース2潮と反対の方向
表層の潮が何らかの原因で下層を流れる潮より遅い場合(又は反対の場合)。
こういうケースはよく二枚潮と呼ばれて非常に釣りをしにくい環境です。
二枚潮の場合は下層の本来の流れに仕掛けが流れていくように、ウキを沈めたり工夫することになります。
しかし、あるポイント一点だけ魚が集まっているのがわかったときや,ウキの位置をあまり変えずに仕掛けだけポイントを通過させたい時などには、ハリスの置き方を変えることでポイント攻略につなげることが可能です。
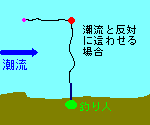
図では仕掛けを左側から振り込み,潮の流れる方向とは反対に這わせます。
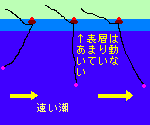
上の図は上層の流れが停滞していると考えて書いています。
ウキ自体が水表層の流れの抵抗でブレーキがかかるため、ウキ下の仕掛けだけが移動してポイントをトレースしていきます。
この方法を用いるのはピンポイントでウキを浮かせてアタリを目で取りたい場合時などに有効だと考えています。
応用として次の様なやり方もあります。
前のページでも少し触れたやり方です。
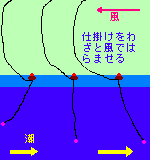
風の抵抗を利用して道糸をはらませてやり,ウキの位置を変えずに,仕掛けだけ移動させてポイントをトレースさせていきます。
ケース3たわませて置く
釣りを行っているときに時として仕掛けをたわませて置くことが有効な場合があります。
潮流が遅い時などは仕掛けを一点に投入することで刺し餌を真っ直ぐに落とし込むことができます。
これは海面に横向きに置くときよりもハリスが水の抵抗を受けない分なじむスピードが速くなります。
水中にそそり立つシモリの壁とかの攻略に使うことがよくあります。
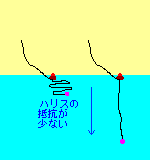
これらのことで注意して欲しいのは、潮流に正対してはわせる置き方は潮流の影響でハリスはゆっくりと沈んでいきます。
つまり、真っ直ぐになるスピードが遅いということです。
一方潮流の方向と反対にはわせる置き方は潮流に押されるためハリスは比較的早くなじもうとします。
つまり、真っ直ぐになるスピードが早いということです。
潮流の方向に正対したから良い置き方、反対だから悪い置き方というのではなく、餌取りの魚の量、本命とする魚の活性(タナ)、潮流のスピードなどの条件によって仕掛けの置き方は変わってきます。
残念ながらこの状況ではこの置き方と言える物が私の頭の中にまだできておらず模索中です。
今までの経験で漠然とはわかっているのですが、これと言えるものがわかれば付け加えていきます。m(_ _)m
2.道糸を置く
次に道糸を置く状況を書いていきます。
キャストした直後は道糸は空中にあるため風の影響を受けやすくなります。
着水したあとは潮流と風の両方の影響を受けます。
風や水の流れなどに影響を受けることは避けて通ることはできませんので、逆にその影響をうまく利用するように工夫します。
潮流が影響する場合の例を挙げてみます。
赤のX印のポイント付近に魚が食い上がってくるのが見えています。
他の場所では全く反応を示しません。
こういう場合どのように仕掛けを投入すればいいでしょうか。
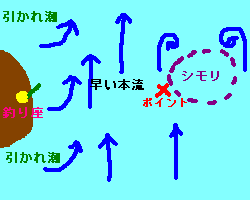
例えば釣り座の前に仕掛けを入れた場合,一旦は引かれ潮に乗って沖に出ますが,早い潮の本筋に乗って上の方へ仕掛け全体が流れていってしまいます。
遠投してダイレクトにポイントへ仕掛けを投入するしかありません。
潮流の影響により流される分を考慮に入れてウキが着水したと同時に潮上へ余分に道糸をたわませて置いてやります。
仕掛けがポイントへ到達して仕掛けがなじむまで、道糸に受ける影響をウキに伝えないようにしてやるのです。
道糸をたわませて置くのでアタリはウキの水没かラインの変化で読み取ることになります。
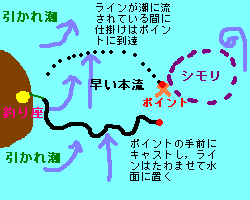
それでは風が道糸に影響を与える場合はどうでしょうか。
下の図は前のページで解説した図です。
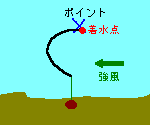
①ただ単に強風下でポイントへキャストしました。
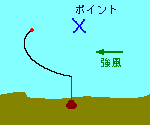
②ウキ下の仕掛けがなじむ頃には強風に道糸があおられ,ポイントからすれてしまいます。
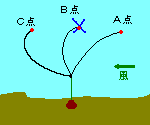
③そこでB点で仕掛けがなじむように考えてA点にキャストします。 しばらくするとC点へ移動しポイントがはずれます。
この様に説明すると仕掛けはうまくポイントに入っているように見えますが、実際にウキ下の仕掛けはどうなっているでしょうか?
あまりにも風の勢いが強すぎるとおそらく下図の様に道糸が引かれてしまい,ハリスは水平になったままで移動し,魚のタナには届かないと思われます。
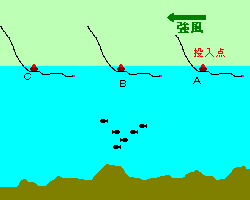
そこで一つの実例ですが,下図の様なキャストを試みます。
風上方向にキャストしてやり,着水と同時にラインを風上の方へ余分に這わせてたるみを作ってやります。
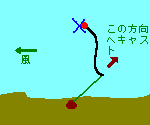
こうすると,風で道糸がはらんで伸びきる間に仕掛けのなじむ時間を与えてやり,少しでも多くの間仕掛けをポイントを保持させるように心掛けます。
このように、道糸はただ単に海面にはわせるだけでなく、周囲の条件を計算に入れて仕掛けに余分な動きを与えないように、道糸が受ける影響をうまく利用して仕掛けの操作へとつなげていくことが必要です。
道糸の置き方はキャスティングに付随する物ですが、海面に置いたあとはラインの操作へとつながっていきます。
事項ではラインの操作について解説します。